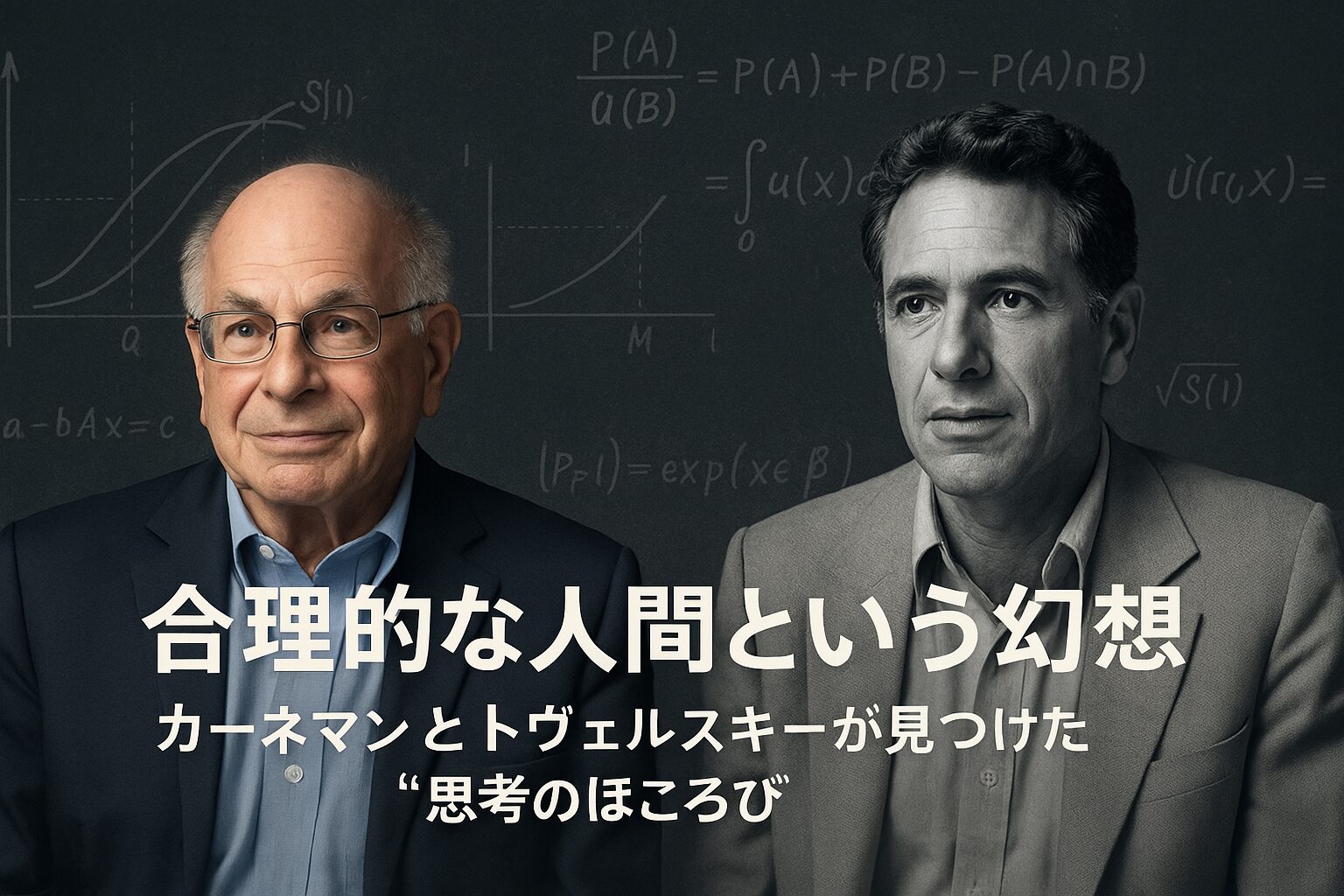「合理的な人間」という幻想を疑った日──カーネマンとトヴェルスキーが見た“思考のほころび”
1. 1960年代、心理学の片隅で
1960年代のイスラエル。
若き心理学者ダニエル・カーネマンは、当時まだ無名の大学教授でした。
第二次世界大戦後の社会は、「人間は理性的に行動する」という経済学の大前提を信じて疑っていません。
その世界では、感情や誤りは“ノイズ”でしかなく、経済モデルに組み込まれることはありませんでした。
しかし、カーネマンは学生の頃から直感的に感じていました。
「人間はそんなに整然と動かない」――と。
彼の関心は、知覚や判断の“錯覚”にありました。
目が騙されるように、思考もまた騙されるのではないか。
この問いが、のちに行動経済学を生む最初の種になります。
2. トヴェルスキーとの出会い
ある日、研究仲間のひとりが紹介したのが、アモス・トヴェルスキー。
軍での経験を経た、快活で論理的な心理学者でした。
ふたりは出会ってすぐに意気投合します。
トヴェルスキーは鋭い理性を持ち、カーネマンは観察と洞察に長けていた。
まるで異なるタイプの頭脳が、ひとつのテーマに出会った瞬間でした。
彼らを結びつけたのは、「人間の判断は、本当に合理的なのか?」という共通の疑問でした。
3. “ヒューリスティック”の発見
ふたりは実験を始めました。
参加者に確率や統計の問題を出し、その答え方を記録する。
驚いたのは、教育レベルの高い被験者たちでさえ、理論的には誤った判断を繰り返すということでした。
人間は論理ではなく、経験則(ヒューリスティック)によって即断してしまう。
たとえば「代表性ヒューリスティック」――
コインを投げて「表・表・表・裏・表」と出たあとに「次も裏が出そう」と思うあの感覚。
確率的には独立しているはずなのに、私たちは“流れ”を感じ取ってしまう。
この小さな実験室での発見が、のちに世界の経済学の根幹を揺るがせることになります。
4. 経済学への“侵入”
当時、経済学はミクロ理論の黄金時代。
人間は合理的に行動し、最大の利益を求める
――この「ホモ・エコノミカス」像が絶対のルールでした。
その世界に、「人間はしょっちゅう間違える」と言い出す心理学者が現れたのです。
学界の反応は冷ややかでした。
論文は経済誌に通らず、心理学界からも「応用性が乏しい」と言われた。
それでも、カーネマンとトヴェルスキーはデータを積み上げていきました。
「ヒューリスティックとバイアス」という論文シリーズを次々に発表し、
1974年、ついに『サイエンス』誌に掲載されます。
このとき初めて、「人間は合理的ではない」という主張が、科学として認められた瞬間でした。
5. “期待効用理論”の修正へ
1980年代初頭、ふたりはさらに一歩踏み込みます。
人が損失を避け、利益よりも痛みに敏感であることを示す「プロスペクト理論」を発表。
「損をしたくない」という感情が、計算よりも行動を強く支配する――
この理論が、従来の「効用最大化モデル」を根底から書き換えました。
プロスペクト理論は、行動経済学の礎石となり、
やがてカーネマンにノーベル経済学賞をもたらします。
トヴェルスキーはその受賞を見届ける前に亡くなりましたが、
カーネマンはこう語っています。
「あの発見のすべては、アモスと私が交わした対話の中にあった」
6. 人間という未完成な存在
彼らが見つけたのは、人間の“欠陥”ではありません。
むしろそれは、古代の脳が残した知恵の名残でした。
私たちは、20万年前に設計された意思決定の回路で、いまだに世界を解釈しています。
行動経済学とは、非合理な行動の学問ではなく、
「なぜその非合理が生まれたのか」を解き明かす人間学でもあるのです。
まとめ
カーネマンとトヴェルスキーが出会ったあの小さな研究室から、
“合理性”という人間観の神話は静かに崩れはじめました。
人間は完璧ではない。
けれど、誤りの中にこそ生存の知恵がある。
その気づきが、行動経済学という新しい地図を生み出しました。
お読みいただきありがとうございます。2人の人間への深い造詣とブレイクスルーをおこすパワーが、行動経済学という面白い分野を作り出しました。「人間を人間のまま扱わなければ、経済行動は説明できない」
この記事と対になる内容を、
同じテーマを“人間の側”から見つめた形で note に書いています。
合わせて読むことで、理解がより立体的になると思います。
興味があれば、そちらもぜひご覧ください。
070 古代の脳──私たちを動かし続ける20万年前の設計図|【FX】Re: Trader
このブログでは、日常のふとした瞬間に感じる「生きづらさ」や、
心身の健康、そして人生を少し面白くする視点について綴っています。
読んでくださった今のあなたにとって、
次に必要な一編がここにあるかもしれません。
もしよろしければ、本棚を少しのぞいてみませんか?
👇 Re: Traderを深く味わうための「最初の一歩」をまとめました 👇